| 1. |
ヴァージニア・ウルフ『ダロウェイ夫人』を読む — パンデミックからディープタイムまで
秦邦生, 小川公代編, 中井亜佐子
(分担執筆)
水声社 2025年9月
(ISBN:9784801008823)
|
| 2. |
遍在するソーシャリズム — 長い二〇世紀の文化研究
川端 康雄, 大貫 隆史, 杉本 裕代, 山田 雄三, 中井 亜佐子他
(分担執筆)
小鳥遊書房 2025年7月
(ISBN:9784867800782)
|
| 3. |
文学理論の名著50
大橋 洋一, 三原 芳秋編, 中井 亜佐子ほか
(分担執筆)
平凡社 2025年3月
(ISBN:9784582703719)
|
| 4. |
エドワード・サイード ー ある批評家の残響
中井 亜佐子
(単著)
書肆侃侃房 2024年1月
(ISBN:9784863856127)
|
| 5. |
日常の読書学 ー ジョゼフ・コンラッド『闇の奥』を読む
中井 亜佐子
(単著)
小鳥遊書房 2023年2月
(ISBN:9784867800089)
|
| 6. |
動物のまなざしのもとで-種と文化の境界を問い直す
鵜飼哲, 中井亜佐子, その他
(分担執筆)
勁草書房 2022年6月
(ISBN:9784326103065)
|
| 7. |
『〈言語社会〉を想像する ー 一橋大学言語社会研究科25周年の歩み』
中井 亜佐子, 小岩 信治, 小泉 順也
(共編者(共編著者))
小鳥遊書房 2022年3月 |
| 8. |
脱領域・脱構築・脱半球 : 二一世紀人文学のために
巽孝之監修, 下河辺美知子ほか編, 中井亜佐子
(分担執筆)
小鳥遊書房 2021年10月
(ISBN:9784909812704)
|
| 9. |
狂い咲く、フーコー : 京都大学人文科学研究所人文研アカデミー『フーコー研究』出版記念シンポジウム全記録+
相澤伸依ほか, 中井亜佐子
(共著)
読書人 2021年8月
(ISBN:9784924671485)
|
| 10. |
『フーコー研究』
小泉 義之, 立木 康介編,中井 亜佐子
(分担執筆)
岩波書店 2021年3月 |
| 11. |
『暗い世界――ウェールズ短編集』
河野真太郎編, 中井 亜佐子
(共訳)
堀之内出版 2020年7月 |
| 12. |
『〈わたしたち〉の到来――英語圏モダニズムにおける歴史叙述とマニフェスト』
中井 亜佐子
(単著)
月曜社 2020年6月 |
| 13. |
『イギリス文学と映画』
中井 亜佐子, 松本 朗他
(分担執筆)
三修社 2019年10月 |
| 14. |
教室の英文学
日本英文学会関東支部, 日本英文学会, 中井亜佐子
(分担執筆)
研究社 2017年5月
(ISBN:9784327472351)
|
| 15. |
ウェンティ・ブラウン『いかにして民主主義は失われていくのか――新自由主義の見えざる攻撃』
中井 亜佐子
(単著)
みすず書房 2017年5月 |
| 16. |
ジェンダーにおける「承認」と「再分配」 ――格差、文化、イスラーム
越智 博美, 河野 真太郎, 中井 亜佐子
(分担執筆)
彩流社 2015年3月
(ISBN:9784779120817)
|
| 17. |
『革命の芸術家――C・L・R・ジェームズの肖像』 (共訳)
ポール・ビュール, 中井 亜佐子, 星野 真志, 吉田 裕
(共訳)
こぶし書房 2014年9月
(ISBN:9784875592938)
|
| 18. |
『デリダと文学』
ニコラス・ロイル, 中井 亜佐子, 吉田 裕
(共訳)
月曜社 2014年6月 |
| 19. |
『一九世紀「英国」小説の展開』
海老根 宏, 高橋 和久, 中井 亜佐子
(共著)
松柏社 2014年6月
(ISBN:9784775401910)
|
| 20. |
ジェンダーと「自由」 ――理論、リベラリズム、クィア
三浦 玲一, 早坂 静, 中井 亜佐子
(共著)
彩流社 2013年3月
(ISBN:9784779118753)
|
| 21. |
文学研究のマニフェスト――ポスト理論・歴史主義の英米文学批評入門
三浦 玲一, 遠藤 不比人, 大田 信良, 越智 博美, 河野 真太郎, 中井 亜佐子, 中山 徹
(共著)
研究社 2012年12月 |
| 22. |
〈終わり〉への遡行――ポストコロニアリズムの歴史と使命 (共編著)
中井 亜佐子, 秦 邦生, 富山 太佳夫, 溝口 昭子, 早川 敦子
(共編者(共編著者))
英宝社 2012年3月
(ISBN:9784269710368)
|
| 23. |
『愛と戦いのイギリス文化史1951-2010 年』
川端 康雄, 中井 亜佐子
(分担執筆)
慶應義塾大学出版会 2011年9月
(ISBN:9784766418781)
|
| 24. |
『ジェンダー表象の政治学――ネーション、階級、植民地』
中井 亜佐子, 吉野 由利
(共編者(共編著者))
彩流社 2011年3月
(ISBN:9784779116087)
|
| 25. |
スピヴァク、日本で語る
C・G・スピヴァク, 鵜飼 哲, 本橋 哲也, 新田 啓子, 竹村 和子, 中井 亜佐子
(共訳)
みすず書房 2009年4月
(ISBN:9784622074472)
|
| 26. |
ジェンダーから世界を読むⅡ ― 表象されるアイデンティティ
中野,知律, 越智博美編, 中井亜佐子
(分担執筆)
明石書店 2008年12月
(ISBN:9784750329062)
|
| 27. |
転回するモダン : イギリス戦間期の文化と文学
遠藤不比人ほか編, 中井亜佐子
(分担執筆)
研究社 2008年7月
(ISBN:9784327472160)
|
| 28. |
『愛と戦いのイギリス文化史1900ー1950 年』
武藤浩史他, 章「アフリカ・カリブ, ヨーロッパ(そして女, ーー帝国周縁の風景より
慶応義塾大学出版会 2007年4月 |
| 29. |
『他者の自伝ーーポストコロニアル文学を読む』
中井亜佐子
研究社 2007年2月 |
| 30. |
『J.M.クッツェーの世界ーー<フィクション>と<共同体>』
田尻芳樹編, 章, 動物のいのち, 文学のことば
英宝社 2006年9月 |
| 31. |
『現代批評理論のすべて』
大橋洋一編, 中井亜佐子
(分担執筆)
新書館 2006年3月 |
| 32. |
<I>Conrad's Europe</I>
Marcin Piechota ed, Asako Nakiai
(分担執筆)
Opole University Publishing House 2005年4月 |
| 33. |
『文化アンデンティティの行方』
中井 亜佐子
(共著)
彩流社 2004年4月 |
| 34. |
『イギリス文学』
中井 亜佐子
(共著)
放送大学 2003年4月 |
| 35. |
<I>The English Book and Its Marginalia: Colonial/Postcolonial Literatures after </I>Heart of Darkness
中井亜佐子
(単著)
Rodopi 2000年4月 |
| 1. |
人文学のアナクロニズム ー なぜいま、エドワード・サイードを読むのか
中井 亜佐子
世界(2024年3月号) 979号234-245頁 2024年2月 |
| 2. |
Materialism, autonomy, intersectionality: revisiting Virginia Woolf through the Wages for Housework perspective
(査読有り)
Asako Nakai
Feminist Theory 24巻4号497-511頁 2022年1月
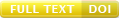


|
| 3. |
小説という名の箱舟のなかで―『ロビンソン・クルーソー』と『フォー』
中井 亜佐子
言語社会 2020年3月 |
| 4. |
旅する理論―エドワード・サイードはフーコーをどう読んだか」
中井 亜佐子
思想 1145号109-123頁 2019年9月 |
| 5. |
革命と日常ーC・L・R・ジェームズにおける「ヴ―ドゥー的大衆」
中井 亜佐子
『多様体』 2018年2月 |
| 6. |
女の日常の詩学ー労働、もの、ことば
中井 亜佐子
アジア太平洋研究 42号87-102頁 2017年11月 |
| 7. |
世界大戦とモダニズムの「晩年」
中井亜佐子
『ヴィクトリア朝文化研究』 13号166-173頁 2015年11月

|
| 8. |
"The 'Unveiled' Woman of New Turkey: Reading Selma Ekrem's Photobiography"
Asako Nakai
Seijo CGS Reports 5号23-36頁 2015年3月 |
| 9. |
Shakespeares sisters in Istanbul: Grace Ellison and the politics of feminist friendship
(査読有り)
Asako Nakai
Journal of Postcolonial Writing 51巻1号22-33頁 2015年1月
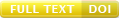
|
| 10. |
「歴史を書くこと、未来を語ること――『ブラック・ジャコバン』と『三ギニー』の同時代性」
中井 亜佐子
『ヴァージニア・ウルフ研究』 29巻29号27-41頁 2012年10月
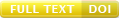
|
| 11. |
"Autobiography of the Other: David Dabydeen and the Imagination of Slavery"
(査読有り)
Asako Nakai
Postcolonial Text 6巻2号1-14頁 2011年10月 |
| 12. |
新しさはいかにして世界に登場するか : 現代英語詩の想像力と近代性
中井 亜佐子
言語社会 5巻79-95頁 2011年3月
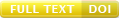

|
| 13. |
モダニズムと(反)自伝 : ヴァージニア・ウルフ「過去の素描」を読む
中井 亜佐子
言語社会 3巻110-127頁 2009年3月
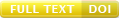

|
| 14. |
"Hybridity and Contemporary Japanese-Language Literature"
Asako nakai
Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences 46巻1号19-29頁 2005年4月
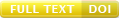

|
| 15. |
ネイション・語り(ナレイション)・世俗批評家 : エドワード・サイードをめぐって
中井 亜佐子
一橋論叢 130巻3号209-225頁 2003年9月
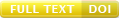

|
| 16. |
Isak Dinesen: The Dark Continent and Its Blank Page
中井亜佐子
The Tsuda Review 43号27-46頁 1998年11月 |
| 17. |
"Journey to the Heart of Darkness: Naipaul's 'Conradian Atavism' Reconsiderd,"
(査読有り)
中井 亜佐子
<I>The Conradion</I> 23巻2号1-16頁 1998年4月 |
| 18. |
" 'I know as much as Sammy Now' : Joyce Cary's Epistemology of Africa".
(査読有り)
中井 亜佐子
Studies in English Literature 1998巻41-51頁 1998年3月 |
| 19. |
"A Kurtz in Malaya: Hugh Clifford's 'Unreasoning' Text"
(査読有り)
中井 亜佐子
<I>Conradiana</I> 29巻3号173-192頁 1997年4月 |
| 1. |
田尻芳樹著『日常という謎を生きる — ウルフ、小津、三島における生と死の感触』(書評)
中井 亜佐子
ヴァージニア・ウルフ研究 45号49-53頁 2025年11月 |
| 2. |
パレスチナ/イスラエル問題の根っこにあるものは? ──植民地主義問題として考える
早尾 貴紀, 中井 亜佐子, 市川 はるみ
じんぶん堂 2025年6月

|
| 3. |
ロバート・ハンプソン著、山本薫訳『評伝ジョウゼフ・コンラッド ー 女性・アメリカ・フランス』(書評)
中井 亜佐子
図書新聞 3680号1頁 2025年3月 |
| 4. |
田尻芳樹著『J・M・クッツェー ー 世界と「私」の偶然性へ』(書評)
中井 亜佐子
英文学研究 101巻146-150頁 2024年12月 |
| 5. |
#327 「エドワード・サイード ある批評家の残響」中井亜佐子
中井 亜佐子
Our Culture, Our View (ラジオ番組) 2024年6月

|
| 6. |
『エドワード・サイード ある批評家の残響』中井亜佐子さんインタビュー 研究・批評通じパレスチナを発信した生涯
篠原 諄也, 中井 亜佐子
好書好日 2024年3月

|
| 7. |
批評とは何か いまサイードを読むこと
中井 亜佐子, 河野 真太郎
週刊読書人 3530号1-2頁 2024年3月 |
| 8. |
モダニズムの時空間
中井 亜佐子
ねむらない樹 9号22-25頁 2022年8月 |
| 9. |
コロナ禍と戦争のさなかに〈わたしたち〉をつなぐ
中井亜佐子
福音と世界 2022年8月号号24-29頁 2022年7月 |
| 10. |
〈新しさ〉はこの世界に可能か ― 移住者たちの文学をめぐる覚書
中井 亜佐子
群像 77巻3号302-309頁 2022年2月 |
| 11. |
エドワード・サイード ― ある批評家の残響
中井亜佐子
群像 76巻7号113-127頁 2021年6月 |
| 12. |
コピー・アンド・ペースト―ヴァージニア・ウルフとともに、仕事をする
中井 亜佐子
群像 75巻12号387-394頁 2020年12月 |
| 13. |
"Narratives of Inequality: Postcolonial Literary Economics By Melissa Kennedy" (Book Review)
Asako Nakai
The Journal of New Zealand Studies N530巻 2020年6月
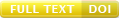

|
| 14. |
Fiction Is History - but Why Fiction? A Response to British Literature in Transition, 1920-1940
Asako Nakai
レイモンド・ウィリアムズ研究 8号 2019年3月 |
| 15. |
C・L・R・ジェームズ「勝利」
中井 亜佐子
多様体 2018年2月 |
| 16. |
女に語らせるということ-リアリズムというおぼろな感覚
中井 亜佐子
『ユリイカ』 2017年12月 |
| 17. |
"Culture and Geography: Travelling Raymond Williams"
Asako Nakai
Raymond Williams Kenkyu 35-40頁 2014年12月 |
| 18. |
座談会 政治的読解の現在 : トランスアトランティック・モダニズム共同討議 (共著)
越智 博美, 河野 真太郎, 中井 亜佐子, 中山 徹, 三浦 玲一
言語社会 5巻8-46頁 2011年3月
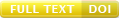

|
| 19. |
モダニズム/モダニティの時空間
中井 亜佐子
言語社会 4巻124-130頁 2010年3月

|
| 20. |
座談会 徹底討論・自伝をめぐって (共著)
桑瀬 章二郎, 坂井 洋史, 中井 亜佐子, 堀尾 耕一, 三浦 玲一, 森本 淳生, 安田 敏朗
言語社会 3巻8-46頁 2009年3月
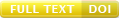

|
| 21. |
「想像のアジア――ウガンダ追放をめぐる女のテクスト」
中井 亜佐子
『英語青年』 151巻5号421-25頁 2005年10月

|
| 22. |
パレスチナからの手紙
中井 亜佐子
英語青年(研究社) 13巻3号209-225頁 2003年4月 |
| 23. |
「海外文学新潮」
中井 亜佐子
『英語青年』 第148巻2号,4号,6号,8号,10号,12号 2002年5月~2003年3月(隔月) 104,221, 366, 496, 616, 745頁 2002年5月 |
| 24. |
クルツ氏は何を意図したかーアチェベ、ダビディーンの誤読
中井 亜佐子
英語青年(研究社) 147巻4号210-214頁 2001年4月 |
| 25. |
ジョイス・ケアリーと「教育のあるアフリカ人」
中井 亜佐子
英語青年(研究社) 142巻9号466-470頁 1996年4月 |
|
No.
|
会議名
|
開催・発表年月日
|
開催地
|
| 1. |
Conrad in the Pacific War: Nakano Yoshio’s 1940 Translation of Heart of Darkness(Modernism and Language: the Fourth International Conference of the Modernist Studies in Asia Network)

|
開催年月日:
2025年6月26日
~ 2025年6月27日
発表年月日:
2025年06月27日 |
Ewha Womans University |
| 2. |
2024年に『オリエンタリズム』を読む(西南学院大学(招待講演))
|
開催年月日:
発表年月日:
2024年05月30日 |
|
| 3. |
Reading Heart of Darkness in Everyday Life(Difficult Conversations in Modernist Studies)
|
開催年月日:
2023年7月25日
~ 2023年8月4日
発表年月日:
2023年07月31日 |
|
| 4. |
中井亜佐子さんと読むジョゼフ・コンラッド『闇の奥』(早稲田大学(招待講演))
|
開催年月日:
発表年月日:
2023年07月05日 |
|
| 5. |
『ダロウェイ夫人』と日常の読書(〈ダロウェイの日〉100周年記念シンポジウム)
|
開催年月日:
発表年月日:
2023年06月04日 |
|
| 6. |
越境文学の夢と幻?(日本英文学会全国大会(シンポジアム第4部門「ブレグジットと英文学」))
|
開催年月日:
発表年月日:
2023年05月20日 |
|
| 7. |
Layered Memories, Intertwined Histories: Personal Narratives in the Season of Politic(Symposium "Literature's Occupations")
|
開催年月日:
発表年月日:
2023年02月13日 |
|
| 8. |
Trafficking, Colonialism, War: Shanghai and Nagasaki in Hayashi Kyoko’s Stories(Networking Pacific-Rim Literatures)
|
開催年月日:
発表年月日:
2022年10月22日 |
|
| 9. |
Intention and Agency in the Television Age: Edward Said’s Transgressive Reading of Raymond Williams(Raymond Williams Centenary Symposia (the Japan Symposium))
|
開催年月日:
発表年月日:
2021年10月22日 |
|
|
No.
|
研究題目
|
研究種目(提供機関・制度)
|
研究期間
|
| 1. |
環太平洋地域における文学ネットワークの構築――歴史・環境・社会運動の観点から
|
基盤研究(C)
(
提供機関:
日本学術振興会
制度:
科学研究費助成事業
)
|
2024年4月
~ 2027年3月 |
| 2. |
ポスト・ブレグジットから見る20世紀英国文化―大都市移住者文化としてのモダニズム
|
基盤研究(B)
(
提供機関:
日本学術振興会
制度:
科学研究費助成事業
)
|
2022年4月
~ 2026年3月 |
| 3. |
ポスト・ブレグジットから見る20世紀英国文化―大都市移住者文化としてのモダニズム
|
基盤研究(B)
(
提供機関:
日本学術振興会
制度:
科学研究費助成事業
)
|
2022年4月
~ 2026年3月 |
| 4. |
英国モダニズムにおける反心理学の系譜に関する学際的かつ国際的研究
|
基盤研究(B)
(
提供機関:
日本学術振興会
制度:
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
)
|
2018年4月
~ 2022年3月 |
| 5. |
「産業文学」の再定義とその国際共同研究─産業化と脱産業化のグローバルな経験
|
基盤研究(A)
(
提供機関:
日本学術振興会
制度:
科学研究費助成事業 基盤研究(A)
)
|
2017年4月
~ 2021年3月 |
| 6. |
英国モダニズムの情動空間に関する総合的かつ国際的研究

|
基盤研究(B)
(
提供機関:
日本学術振興会
制度:
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
)
|
2013年4月
~ 2017年3月 |
| 7. |
モダニズムの越境性/地域性――近代の時空間の再検討

|
基盤研究(B)
(
提供機関:
日本学術振興会
制度:
科学研究費助成事業
)
|
2011年4月
~ 2015年3月 |
| 8. |
ヴィクトリア朝以降の英国ナショナル・アイデンティティ構築に関する融合的研究
|
基盤研究(B)
(
提供機関:
日本学術振興会
制度:
科学研究費助成事業
)
|
2009年
~ 2012年 |
| 9. |
モダニズムと自伝――自己表象をめぐる理論構築の過程

|
基盤研究(C)
(
提供機関:
日本学術振興会
制度:
科学研究費助成事業
)
|
2008年4月
~ 2011年3月 |
| 10. |
ポスト植民地主義思想は「英文学」をどう変えたか

|
若手研究(B)
(
提供機関:
日本学術振興会
制度:
科学研究費助成事業
)
|
2002年4月
~ 2005年3月 |